春の訪れとともに野山や水辺でせりが繁茂し始める七十二候の一つ、芹乃栄(せりすなわちさかう)。水辺の植物が力強く成長する様子は、春の生命力を象徴します。例年は3月上旬から中旬にあたります。
芹乃栄とはどんな季節?
七十二候は一年を72に分け、自然や生き物の微細な変化を表す日本独自の暦です。芹乃栄は春分の前後の次候で、せりが水辺や湿地で勢いよく生長する時期を指します。春の息吹を感じる象徴的な季節です。
水辺のせりは、冬の間に蓄えた生命力を使って一気に芽を伸ばします。野山や川辺でせりが緑を広げる様子は、春の到来を五感で実感できる自然のサインです。
芹乃栄の季節は、野山や水辺で春の息吹を感じながら散策するのに最適な時期です。小さな植物の成長を観察することで、自然の循環や季節の移ろいを意識することができます。
せりと自然のリズム
せりの生長は、水温や日差しの増加に敏感に反応します。水辺の環境が整うことで、せりだけでなく周囲の生態系全体も活発になり、昆虫や小動物の活動も見られるようになります。
水辺の植物が繁茂することで土壌や水の状態も改善され、自然界の循環が活発化します。芹乃栄の現象は、春の自然界の活動再開を象徴するサインとして理解できます。
古来、せりは食材としても利用され、春の味覚として親しまれてきました。自然の成長を生活に取り入れ、食卓で季節感を楽しむ知恵として活用されてきたのです。
暮らしで芹乃栄を楽しむ方法
野山や水辺を散策して、せりの緑が広がる様子を観察するだけでも春を感じられます。小さな植物の生長に目を向けることで、生活の中に自然のリズムを取り入れることができます。
せりを摘んで料理に活用するのもおすすめです。季節の食材として春の息吹を味わうことで、自然とのつながりを生活の中で実感できます。
写真やスケッチでせりの生長を記録することで、季節の変化を後から振り返る楽しみも生まれます。芹乃栄の季節は、自然の営みを生活に取り入れる絶好の機会です。
芹乃栄が教えてくれる春の息吹
芹乃栄は、冬の静けさから春の活力への移行を象徴する七十二候です。水辺のせりが勢いよく生長する様子は、自然界全体の春の息吹を実感させてくれます。
忙しい日常でも、水辺や野山の小さな変化に目を向けることで、季節感を意識する習慣が生まれます。自然のリズムを生活に取り入れることで、心にゆとりや季節の彩りが加わります。
次に野山や水辺でせりの緑を見かけたときは、春の息吹を感じながらゆったりとした時間を過ごしてみてください。芹乃栄の季節は、身近な自然の変化を楽しむ絶好の機会です。
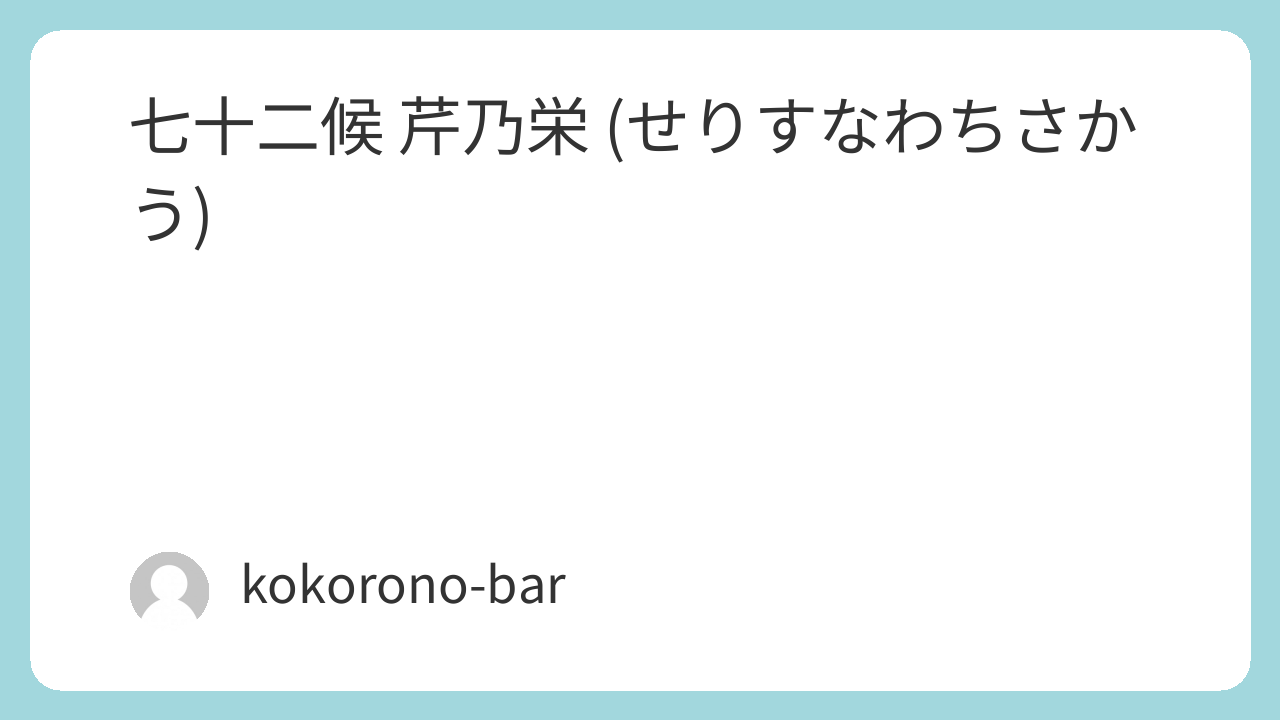


コメント