七十二候「乃東枯(なつかれくさかるる)」は、夏枯草(ウツボグサ)が枯れ始める頃を表します。初夏の生命力あふれる季節に、ひとつの草が静かに役目を終える自然のリズムです。
乃東枯とはどんな季節か
「乃東枯」は二十四節気「夏至」の初候にあたり、例年6月下旬頃に訪れます。昼が最も長い時期でありながら、自然は次の循環に向けて準備を始めます。
この候に枯れる「乃東」とは、薬草として知られるウツボグサのことです。花を咲かせた後、夏至の頃に姿を変えていきます。
力強い夏の始まりの中に、小さな移ろいを感じる節目が「乃東枯」なのです。
夏枯草(ウツボグサ)の特徴
ウツボグサはシソ科の多年草で、紫色の花穂をつける美しい植物です。花が終わると枯れたように見えるため「夏枯草」と呼ばれます。
この変化は、夏の盛りにあっても命が移ろっていく自然の循環を象徴しています。
「乃東枯」という候は、目立たない草花にも光を当てる日本人の繊細な感性を映しています。
薬草としての役割
ウツボグサは古来より薬草として用いられ、解熱や消炎の効果があるとされてきました。漢方では「夏枯草」と呼ばれています。
身近な野草が人々の健康を支えていた歴史は、自然と共に生きてきた暮らしを物語っています。
乃東枯の候は、植物が持つ力を生活に取り入れてきた先人の知恵を感じさせてくれます。
自然の循環と日本人の感性
夏至という陽の極みに、草が枯れるという対照的な現象は、自然のバランスや無常を象徴する出来事です。
日本人はこうした小さな変化を季節の兆しとして感じ取り、暦や文化に反映させてきました。
乃東枯は、自然の循環に寄り添いながら暮らす感性を思い出させる候といえるでしょう。
乃東枯を日常に取り入れる
庭や野原でウツボグサを見かけたら、その変化を観察してみると季節の移ろいを実感できます。
また、薬草や漢方の知識を学び、自然の恵みを日常に取り入れることも暮らしを豊かにする工夫です。
七十二候「乃東枯」を意識することで、日常の中に自然の循環を感じ、より丁寧に季節を味わえるでしょう。
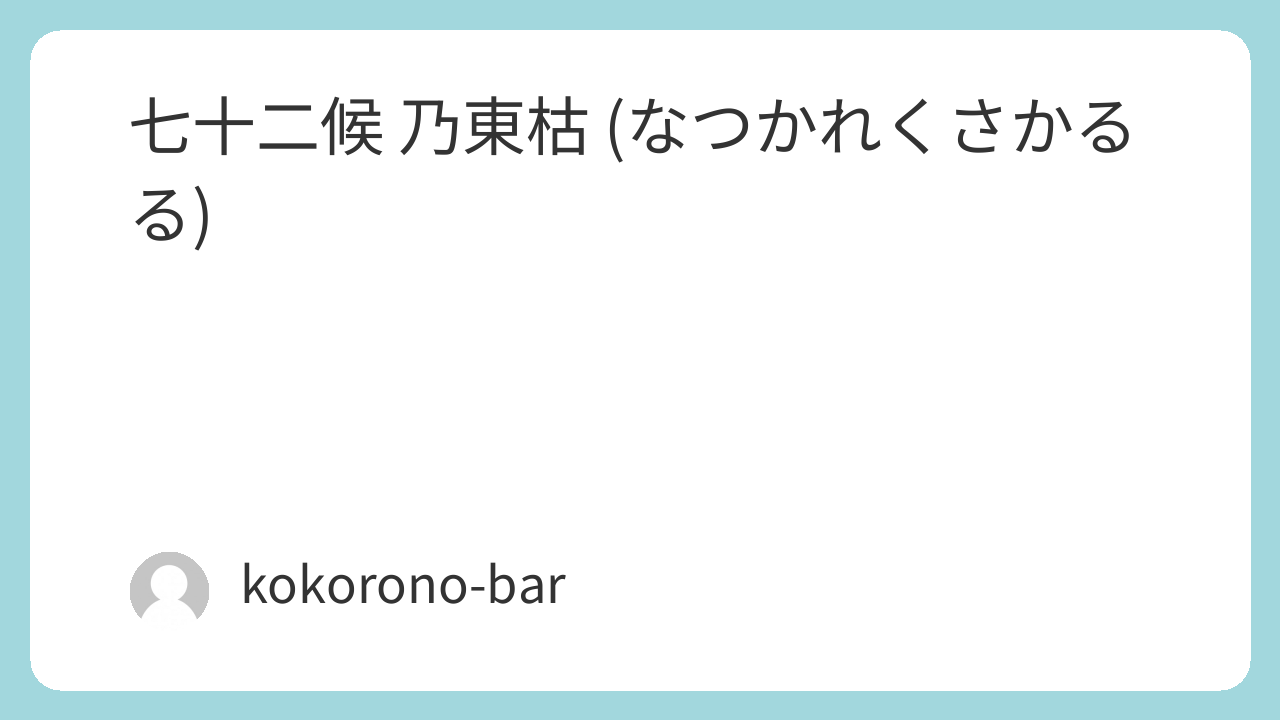


コメント