七十二候「鶺鴒鳴(せきれいなく)」は、秋分の初候にあたり、セキレイが澄んだ声で鳴き始める頃を表します。秋の訪れを告げる鳥の姿と声が、季節の移ろいをやさしく伝えてくれます。
鶺鴒鳴とはどんな季節か
「鶺鴒鳴」は二十四節気「秋分」の初候で、9月下旬頃にあたります。昼と夜の長さがほぼ同じになり、自然界は秋の気配を深めていきます。
この時期、セキレイが川辺や田畑でよく見られ、澄んだ鳴き声が響くようになります。季節の移ろいを告げる存在として親しまれてきました。
秋の始まりを鳥の声で感じ取る感性は、自然と共に暮らしてきた日本人ならではのものです。
セキレイという鳥の特徴
セキレイは、白や黒、黄色のコントラストが美しい小鳥で、尾を上下に振る姿が特徴的です。その愛らしい動きから「庭鳥」とも呼ばれました。
川辺や水辺を好み、澄んだ鳴き声を響かせながら飛び回ります。その姿は、古来より季節を告げる鳥として人々に親しまれています。
セキレイの鳴き声は、秋の訪れを象徴する自然の音色として心に響きます。
セキレイと日本文化
セキレイは古事記にも登場する鳥で、「夫婦和合」を教えた鳥として伝えられています。縁結びや家庭円満の象徴としても崇められてきました。
また、和歌や俳句の題材としても詠まれ、季節の風情を表す存在となっています。文学や芸術における役割も大きい鳥です。
「鶺鴒鳴」の候は、ただの自然現象ではなく、文化や信仰にも結びついた重要な節目です。
暮らしに息づくセキレイの存在
農村ではセキレイが害虫を食べてくれることから、稲作の守り鳥とされてきました。人と自然の共生を象徴する存在です。
その鳴き声は、人々にとって日常の中の季節の合図でもありました。自然とともに暮らす知恵がそこに息づいています。
セキレイは現代でも身近に観察できる鳥で、四季折々の自然を感じるきっかけを与えてくれます。
鶺鴒鳴を日常に取り入れる
都会でも川辺や公園でセキレイの姿を見かけることがあります。自然観察を楽しむことで、候の意味を体感できます。
また、古来の物語や俳句を調べながら、セキレイの声に耳を澄ませれば、自然との距離がぐっと近づくでしょう。
七十二候「鶺鴒鳴」を意識することは、日常の中に小さな季節の彩りを見つける第一歩となります。
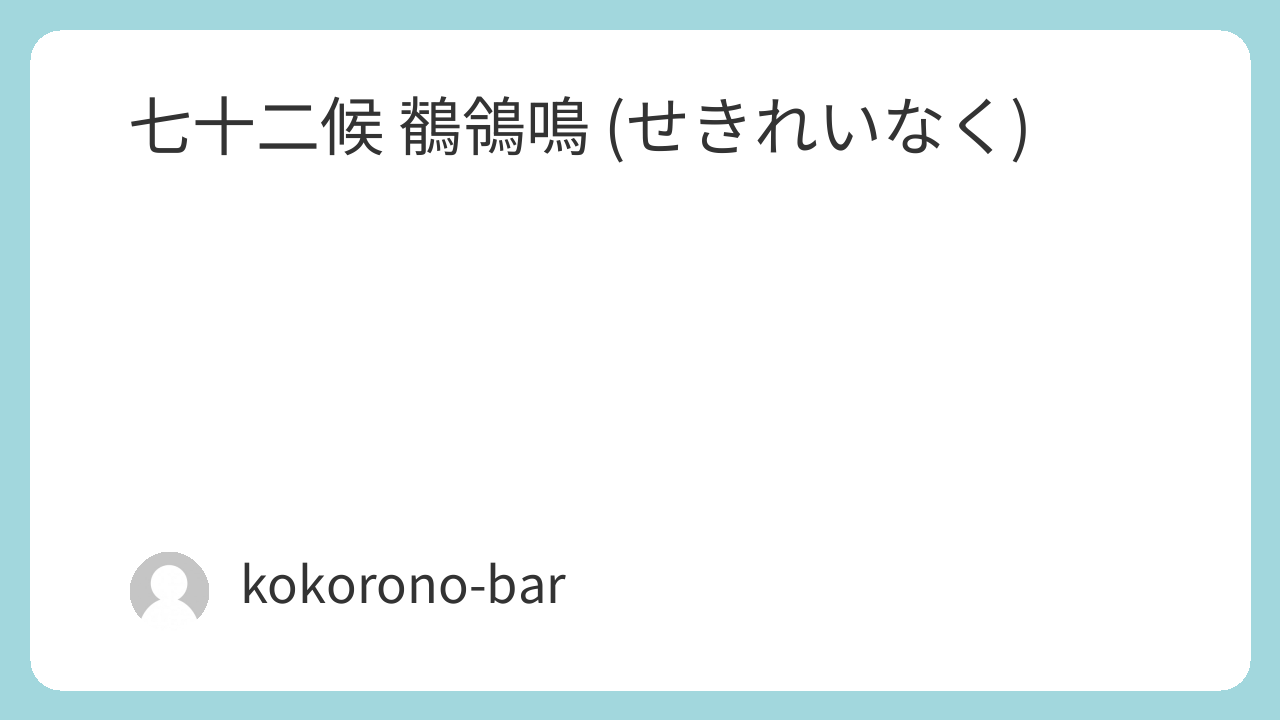


コメント