七十二候「玄鳥去(つばめさる)」は、春に渡来した燕が南へ帰る季節を表します。人々に親しまれてきた燕の姿が消える頃、秋の深まりと別れの気配を感じさせてくれます。
玄鳥去とはどんな季節か
「玄鳥去」は二十四節気「秋分」の次候にあたり、9月下旬から10月初め頃を示します。春から夏にかけて日本で子育てをしていた燕たちが、南の国へ帰る時期です。
燕はシベリアや東南アジアを行き来する渡り鳥で、その行動は季節の移ろいを知らせる自然の暦の一部でした。
玄鳥去の候は、夏のにぎわいから秋の静けさへと移る節目として、大切に受け止められてきました。
燕と日本人の暮らし
燕は古くから人々に親しまれてきました。家の軒先に巣をつくる燕は「幸福を運ぶ鳥」とされ、吉兆の象徴とされました。
また、農村では害虫を食べてくれる存在として大切にされ、田畑を守る仲間のように考えられていました。
燕の去来は、自然とともに暮らす日本人の感性を映し出し、身近な存在であり続けてきたのです。
燕が去ることの意味
燕の姿が見えなくなるのは、季節の変化を実感する大きなきっかけです。別れの寂しさとともに、自然の循環を感じさせてくれます。
古来より「燕の去る頃は秋も深まる」とされ、暦や歳時記にもしばしば登場しました。燕は人々の季節感と文化に深く関わっています。
燕の渡りは、自然界の大きな営みを映す現象であり、人と自然とのつながりを再認識させてくれる出来事です。
文学や芸術に見る燕
燕は多くの和歌や俳句に詠まれ、春の訪れや秋の別れを象徴する題材となってきました。小さな姿に大きな季節感を託したのです。
また、絵画や民話でも親しまれ、家族愛や希望の象徴として描かれることも少なくありませんでした。
「玄鳥去」という候には、燕と人との絆や、自然の中での暮らしの在り方が表現されています。
玄鳥去を日常に取り入れる
現代では燕の渡りを直接意識する機会は少ないかもしれませんが、季節の区切りを知る手がかりとして心に留めることはできます。
秋の夜長に燕の姿を思い浮かべながら、読書や散歩を楽しむことも、自然と調和する暮らしの一工夫です。
「玄鳥去」を意識することで、季節の変化を丁寧に感じ取り、自然とともにある時間を過ごせるでしょう。
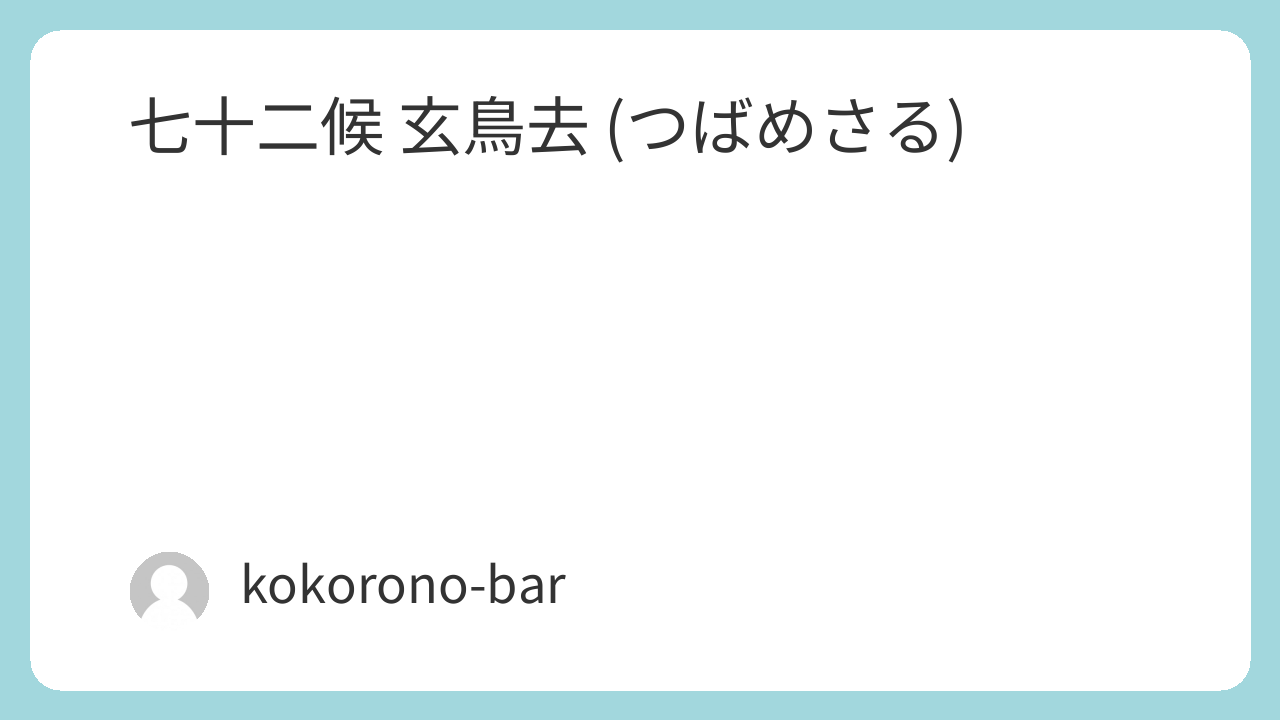


コメント