七十二候「蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)」は、虫たちが冬ごもりのために地中へと姿を隠す季節を表します。自然界が静まり、冬の足音が一歩ずつ近づいてくる頃です。
蟄虫坏戸とはどんな季節か
「蟄虫坏戸」は二十四節気「立冬」の初候にあたり、例年11月上旬頃を指します。虫たちが土中に潜り込み、戸を閉ざすように冬ごもりを始める時期です。
夏から秋にかけて活動していた虫たちが姿を消し、自然界は静けさを増していきます。季節の移ろいが実感できる瞬間です。
この候は、生命が休息へと向かう様子を映し出し、自然界の循環を示す大切な節目です。
虫たちの冬ごもりの意味
冬ごもりは、虫たちが寒さを乗り越えるための生きる知恵です。土や落ち葉の下で、春の再び訪れる日を待っています。
小さな生き物たちが戸を閉ざす姿には、自然界の秩序や生存の工夫が感じられます。そこには命のたくましさが宿っています。
「蟄虫坏戸」という言葉には、自然界の営みを観察し、季節を丁寧に受け止めてきた人々のまなざしが表れています。
暮らしに見られる季節の変化
虫の声が聞こえなくなると、秋の終わりと冬の到来を強く意識するようになります。日常の中の小さな変化が、季節を知らせてくれます。
農村では冬支度が始まり、保存食の準備や囲炉裏の使用など、暮らしのリズムも冬仕様に切り替わっていきます。
自然の動きに合わせて人々も行動を変えることは、七十二候の知恵が今も息づいている証といえるでしょう。
日本文化と虫の関わり
日本では古くから、虫の音を「声」として愛で、詩や歌に詠まれてきました。虫は身近な自然の象徴でもあります。
「蟄虫坏戸」の頃になると、その声も静まり、寂しさとともに季節の深まりを感じさせてくれます。
虫の存在は、自然とともに暮らす文化や感性を育んできた大切な要素であり、今もなお私たちの心に残されています。
蟄虫坏戸を日常に取り入れる
現代では虫の冬ごもりを身近に感じにくいかもしれませんが、自然のリズムを意識することは可能です。散歩中に静まりゆく景色を観察してみましょう。
また、旬の食材や季節の行事を取り入れることで、この時期特有の季節感を楽しむことができます。冬支度を始める良い合図にもなります。
七十二候「蟄虫坏戸」を意識する暮らしは、自然と調和しながら過ごす豊かさを思い出させてくれるでしょう。
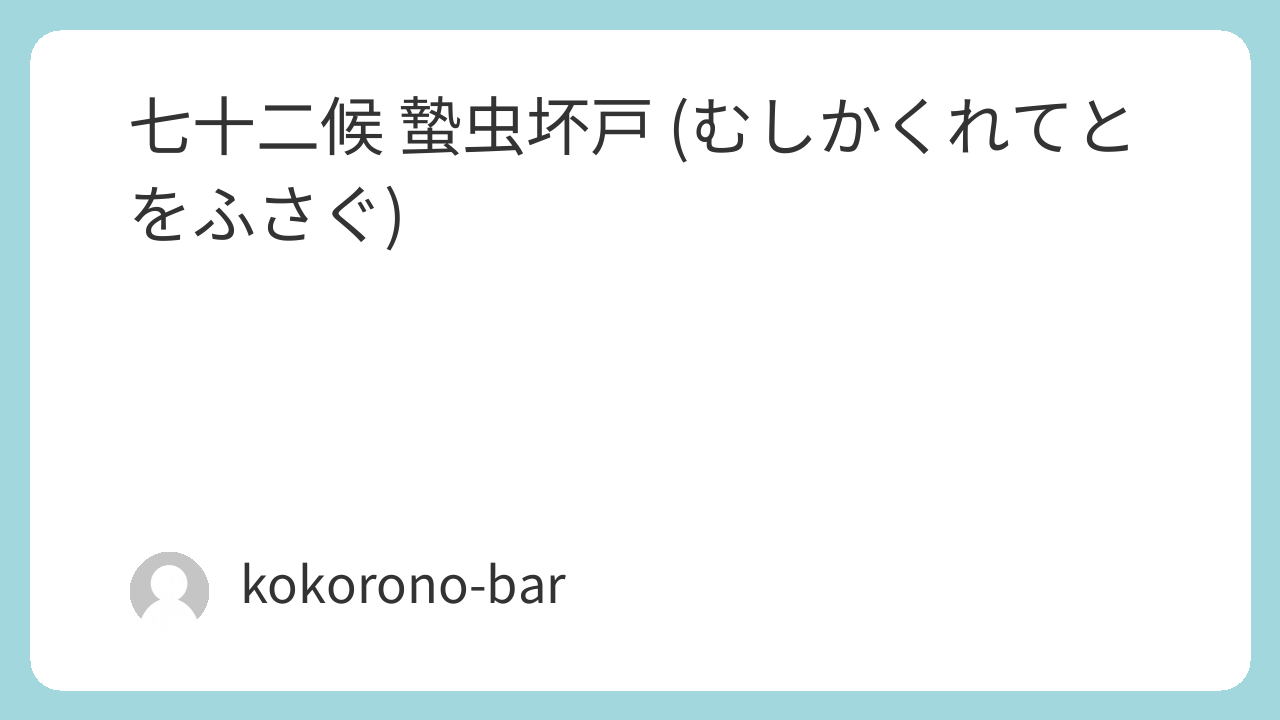


コメント