七十二候「鴻雁来(こうがんきたる)」は、シベリアから渡り鳥の雁が日本へ飛来する季節を表す言葉です。秋の深まりとともに、空を渡る鳥たちが季節の移ろいを告げてくれます。
鴻雁来とはどんな季節か
「鴻雁来」は二十四節気「寒露」の初候にあたり、例年10月上旬から中旬頃に見られる現象です。北の国から雁が日本へと渡ってきます。
夏をシベリアで過ごした雁たちは、冬を越すために温暖な地を求めて南下します。その姿は、古くから人々に秋の風物詩として親しまれてきました。
澄んだ秋空を群れで飛ぶ雁は、自然のリズムを映す存在であり、季節の移り変わりを感じさせてくれます。
雁の渡りに込められた意味
雁は古来より「季節を運ぶ鳥」とされ、和歌や俳句にもたびたび詠まれてきました。群れをなして飛ぶ姿は、秋の象徴です。
また、雁は「文を運ぶ鳥」とも呼ばれ、遠方との絆や手紙の象徴としても親しまれてきました。旅立ちや再会を想起させる鳥でもあります。
「鴻雁来」という候は、単に自然現象を表すだけでなく、人と自然、そして人と人とのつながりを映す言葉でもあります。
暮らしの中での雁の存在
雁は古来、農耕の営みとも関わってきました。田畑に降り立つ姿は豊穣を連想させ、人々に安心感を与えてきました。
一方で、食用や狩猟の対象でもあり、暮らしの糧を支える存在でもありました。自然との共生が生活に息づいていたのです。
現在では、保護活動や観察の対象となり、バードウォッチングなどを通じて人々の心を豊かにしています。
雁が訪れる地域と風景
日本各地で雁の飛来地として知られる場所があります。代表的なのは宮城県の伊豆沼や新潟の瓢湖など、渡り鳥の楽園と呼ばれる場所です。
夕暮れ時に群れで飛び立つ「ねぐら立ち」の光景は圧巻で、多くの人々を魅了してきました。自然の営みが織りなす壮大な舞台です。
旅の途中で立ち寄る雁の姿は、その土地の季節の移ろいを映し出し、地域の文化や観光にもつながっています。
鴻雁来を日常に感じる工夫
渡り鳥の姿を直接見る機会は限られますが、自然観察や写真、俳句などを通じて季節を味わうことができます。
秋空を見上げる習慣を持つだけでも、雁の渡りを想像し、自然とともにある時間を楽しめるでしょう。
七十二候「鴻雁来」を意識することで、自然のリズムに寄り添い、日々の暮らしの中に季節感を豊かに取り入れることができます。
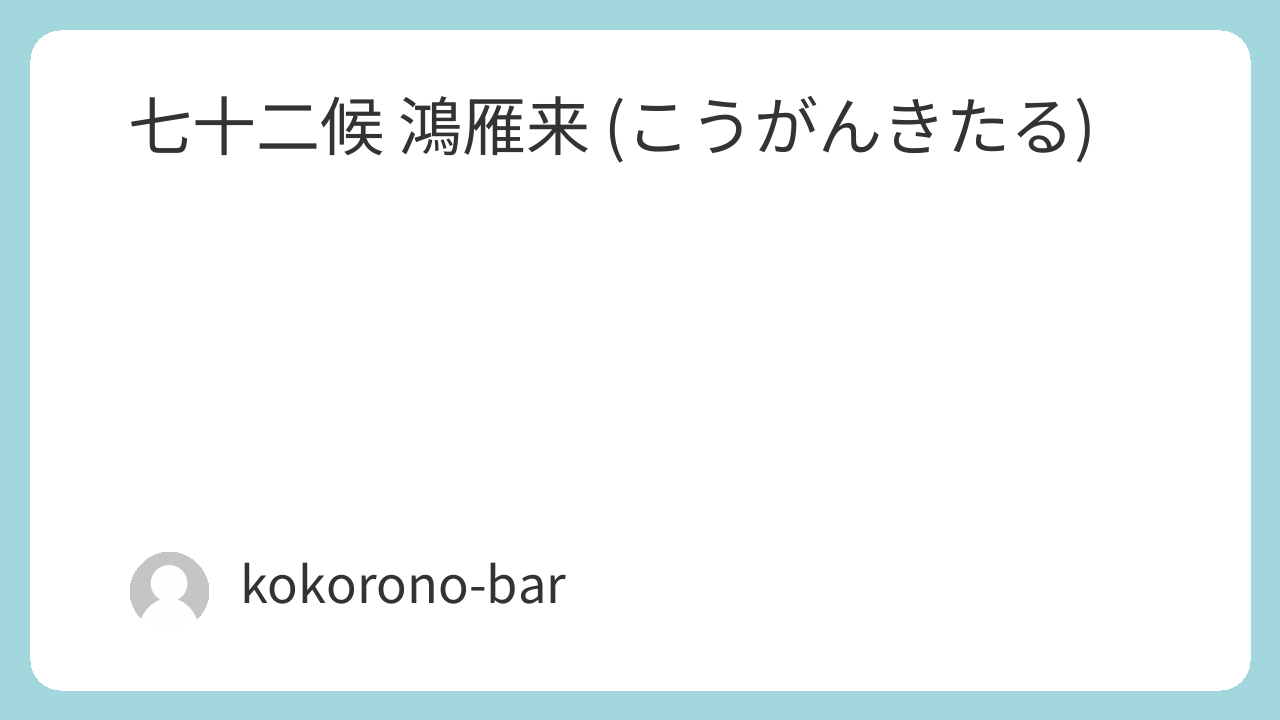


コメント