 七十二候
七十二候 第三十一候 温風至 (あつかぜいたる) | 七十二候
七十二候「温風至(あつかぜいたる)」は、夏の熱気を帯びた南風が吹き始める頃を表します。いよいよ夏本番を迎え、自然も人々の暮らしも活気に満ちる季節です。 温風至とはどんな季節か 「温風至」は二十四節気「小暑」の初候にあたり、例年7月上旬頃を示...
 七十二候
七十二候 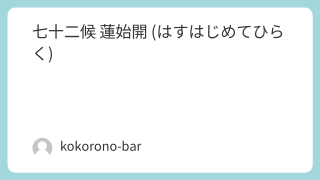 七十二候
七十二候 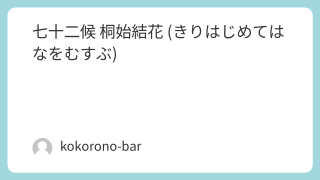 七十二候
七十二候 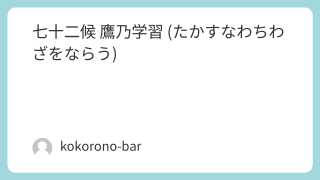 七十二候
七十二候 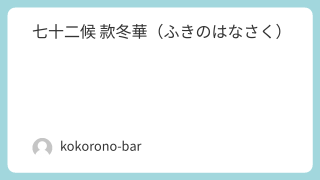 七十二候
七十二候 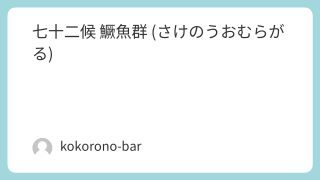 七十二候
七十二候 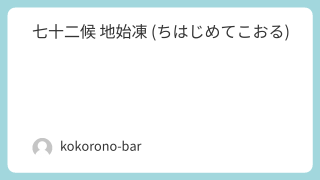 七十二候
七十二候 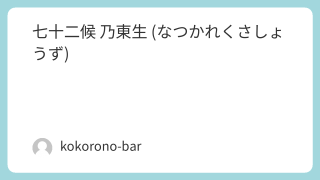 七十二候
七十二候 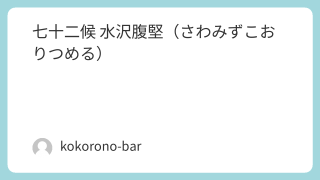 七十二候
七十二候  七十二候
七十二候