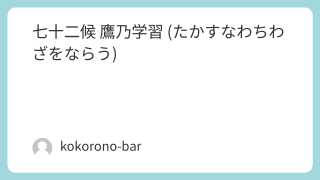 七十二候
七十二候 第三十三候 鷹乃学習 (たかすなわちわざをならう) | 七十二候
七十二候「鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)」は、鷹の雛が飛び立ちの練習を始める頃を表します。夏の盛りに、命の営みが受け継がれる力強い瞬間が訪れます。 鷹乃学習とはどんな季節か 「鷹乃学習」は二十四節気「小暑」の末候にあたり、例年7月中旬...
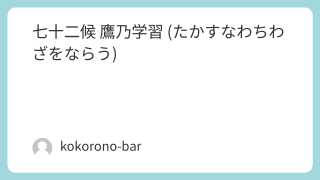 七十二候
七十二候 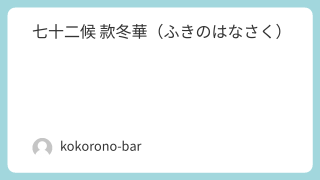 七十二候
七十二候 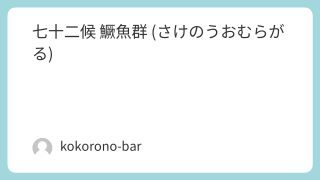 七十二候
七十二候 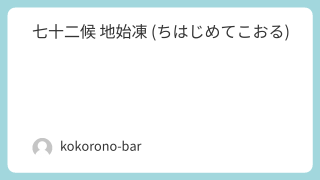 七十二候
七十二候 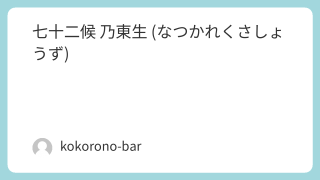 七十二候
七十二候 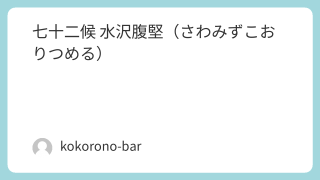 七十二候
七十二候  七十二候
七十二候  七十二候
七十二候 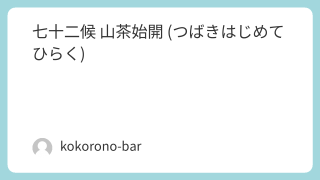 七十二候
七十二候 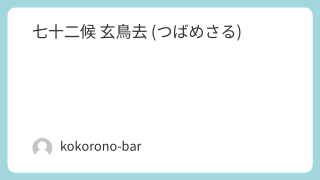 七十二候
七十二候