 四季・暦
四季・暦 春分・秋分・夏至・冬至の意味とは?立春・立夏・立秋・立冬もわかる二十四節気入門
季節の変化をもっと身近に感じたい方へ。春分・秋分・夏至・冬至、そして立春・立夏・立秋・立冬など、1年を24に分けた「二十四節気」を知ると、自然のリズムに合わせた暮らしや行事、食文化を楽しむことができます。本記事では、二十四節気の意味や違い、...
 四季・暦
四季・暦 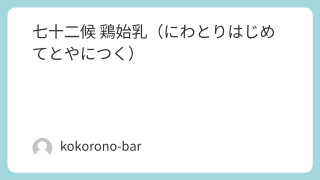 七十二候
七十二候 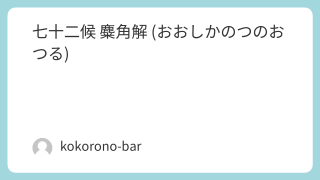 七十二候
七十二候 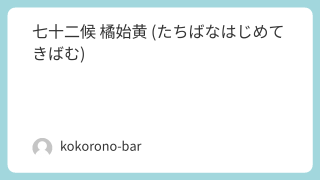 七十二候
七十二候  七十二候
七十二候  七十二候
七十二候 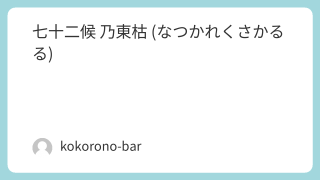 七十二候
七十二候  七十二候
七十二候 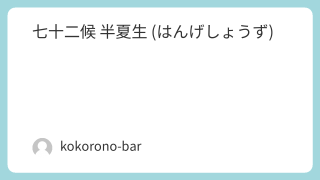 七十二候
七十二候 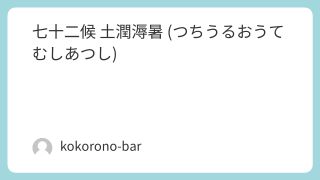 七十二候
七十二候