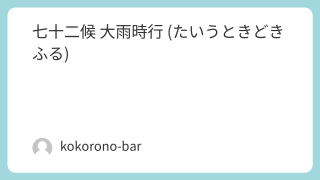 七十二候
七十二候 第三十六候 大雨時行 (たいうときどきふる) | 七十二候
七十二候「大雨時行(たいうときどきふる)」は、夏の盛りに激しい夕立やにわか雨が降る頃を表します。入道雲から突然降り注ぐ雨は、大地を潤し、夏から秋への移ろいを告げます。 大雨時行とはどんな季節か 「大雨時行」は二十四節気「大暑」の末候にあたり...
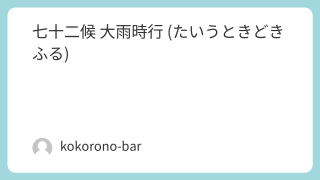 七十二候
七十二候 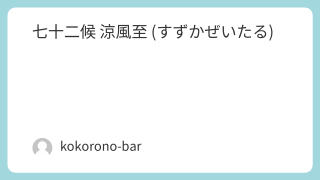 七十二候
七十二候 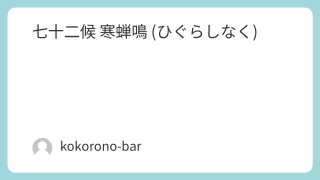 七十二候
七十二候 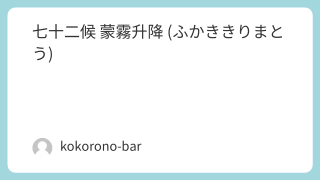 七十二候
七十二候 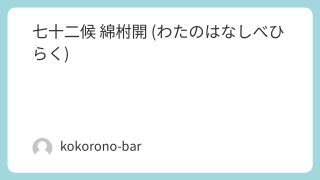 七十二候
七十二候 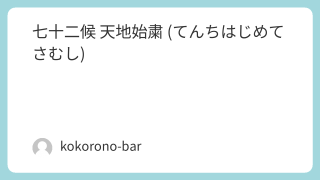 七十二候
七十二候 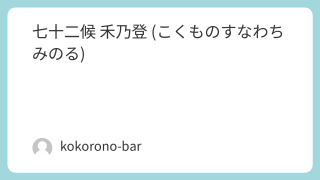 七十二候
七十二候 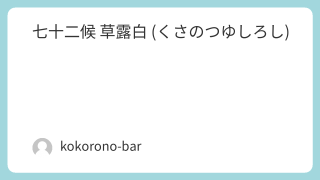 七十二候
七十二候 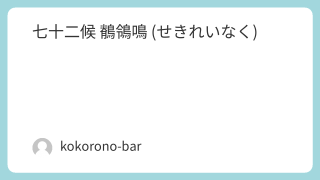 七十二候
七十二候 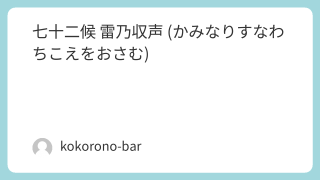 七十二候
七十二候