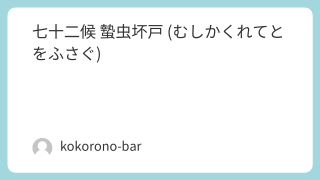 七十二候
七十二候 第四十七候 蟄虫坏戸 (むしかくれてとをふさぐ) | 七十二候
七十二候「蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)」は、虫たちが冬ごもりのために地中へと姿を隠す季節を表します。自然界が静まり、冬の足音が一歩ずつ近づいてくる頃です。 蟄虫坏戸とはどんな季節か 「蟄虫坏戸」は二十四節気「立冬」の初候にあたり、例年...
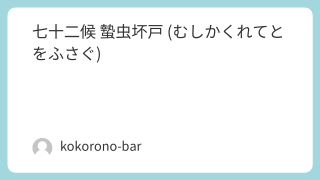 七十二候
七十二候 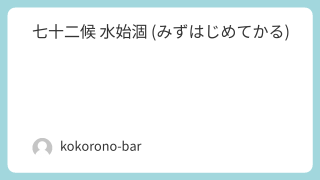 七十二候
七十二候 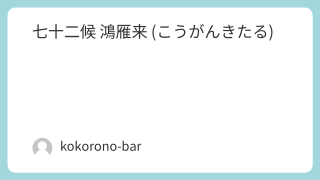 七十二候
七十二候  七十二候
七十二候 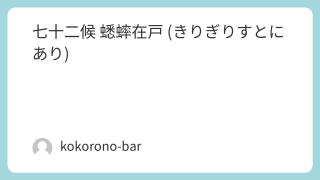 七十二候
七十二候 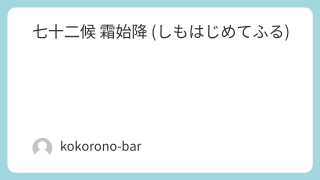 七十二候
七十二候 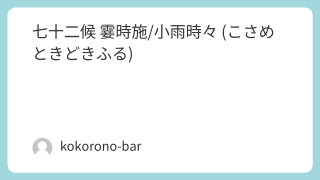 七十二候
七十二候 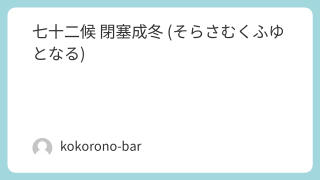 七十二候
七十二候 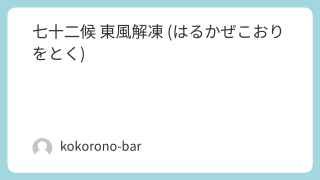 七十二候
七十二候 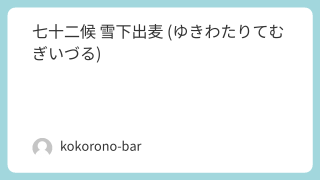 七十二候
七十二候